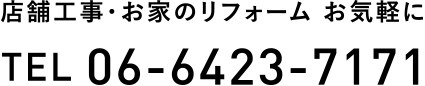寿司屋を開業するのに資格は必要ですか?
寿司屋を開業する場合は「食品衛生責任者」の資格が必要です。
目次
寿司屋の開業に必要な資格

寿司屋などの飲食店を開業する場合に必要な資格は「食品衛生責任者」です。
1店舗に1人は食品衛生責任者の資格保持者が必要なので、独立開業を検討している人は取得しておくとよいでしょう。
栄養士や調理師、製菓衛生師などの資格がある人を除き、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得できます。
また、収容人数が従業員を含めて30名以上の店舗で開業する場合は、「防火管理者」の資格も必要です。
店舗の延べ面積により「甲種」「乙種」のどちらかを取得して、管轄の消防署に届け出る必要があります。
寿司職人になるための資格はなく、学歴も問われません。
寿司職人になるには、経験を積んで知識や技術を身につける必要があります。
飲食店の開業に必要な資格「食品衛生責任者」や「防火管理者」の資格については以下の記事も参考にしてみてください。
-

-
居酒屋を開業するのに必要な資格ってあるの?
目次1 居酒屋開業に必要な資格・届出①:食品衛生責任者2 居酒屋開業に必要な資格・届出②:防火管理者3 居酒屋開業に必要な資格・届出③:深夜酒類提供飲食店営業4 居 […]
続きを見る
-

-
ラーメン屋の開業に調理師免許は必要?【資格】
目次1 ラーメン屋の開業に必要な資格①:食品衛生責任者2 ラーメン屋の開業に必要な資格②:防災管理者3 ラーメン屋の開業にあるといい資格:ラーメン検定4 ラーメン屋 […]
続きを見る
【寿司屋開業】寿司職人を目指す方法①:弟子入りする

寿司職人を目指す方法は2つあります。
ひとつ目は、寿司屋に弟子入りして働きながら技術を身につける方法です。
弟子入りして修行する方法は職人の世界では一般的で、時間をかけてじっくりと技術を学べるというメリットがあります。
寿司の握り方だけでなく、魚市場での仕入れ方や魚の目利き、お客のあしらい方など、寿司職人に必要とされる多くの知識を学べるのもメリットです。
また、高くはありませんが、働いた分のお給料をもらうことができる点もメリットといえるでしょう。
デメリットとしては、修業期間や拘束時間が長いことが挙げられます。
【寿司屋開業】寿司職人を目指す方法②:専門学校に通う

寿司職人を目指す方法の2つ目は、寿司職人を養成する専門学校に通う方法です。
弟子入りの場合、修業期間は10年といわれていますが、専門学校なら数ヶ月~と短い期間で技術を身につけることができます。
魚の選び方、さばき方、握り方といった基本的な技術をすぐに学べるため、早く寿司職人になりたい人に向いているでしょう。
卒業後の就職や開業のサポートを受けられる点もメリットです。
ただし専門学校ですので学費がかかります。
また寿司職人養成の専門学校は数が少なく、家から通える範囲にあるとは限りません。
学費以外に生活費などもかかる可能性があるので覚えておくとよいでしょう。
専門学校によってコース内容や期間、学費などが異なります。
弟子入りではなく専門学校で学んで寿司職人を目指す場合は、ウェブサイトなどで詳しく調べてみてください。
寿司屋の開業にあるといい資格

寿司屋の開業に必須の資格はありませんが、次の資格があるとさまざまなメリットがあります。
調理師免許
調理師免許とは国家資格のひとつで、食品や栄養、衛生に関わる正しい知識があることを証明することができる資格です。
社会的信用を得られる、活躍する場を広げられるなどのメリットのほか、寿司屋の開業に必要な食品衛生責任者の資格を申請のみで取得できるというメリットがあります。
ふぐ調理師免許
ふぐ調理師免許とは、ふぐ料理をお客に提供するために必要な資格で、国家資格ではなく各都道府県で定められた資格です。
安全で衛生的な仕事ができる、一定以上の知識と実力があることの証明になるといえるでしょう。
ふぐ調理師免許があれば、高級魚であるふぐを扱う寿司屋を開業することも可能です。
まとめ

この記事では、寿司屋の開業に必要な資格についてご紹介しました。
まとめ
・寿司屋などの飲食店を開業する場合は「食品衛生責任者」の資格が必要
・寿司職人を目指す方法①弟子入りして修行を積む
・寿司職人を目指す方法②専門学校で学ぶ
・寿司屋の開業にあるといい資格:調理師免許、ふぐ調理師免許
寿司屋の開業に必要な資格について詳しく知りたい人は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。